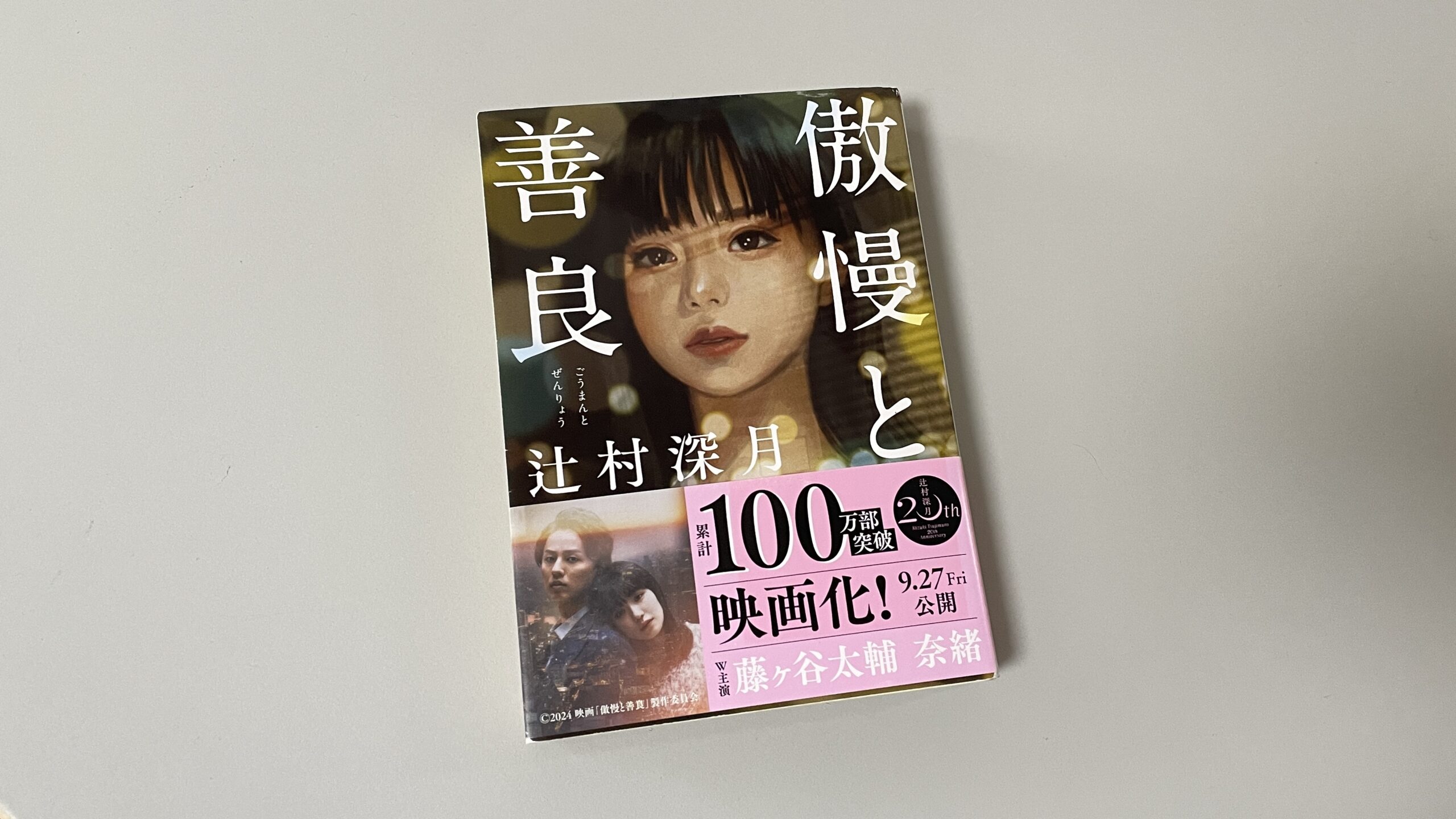辻村深月さんの『傲慢と善良』を読みました。最近、自己肯定感や自尊心、承認欲求などについて考えることが多くて、色々とネットで記事を読んでいるとこの小説に辿り着きました。2024年9月に映画化されていたようで、たまたま飛行機の視聴コンテンツにもあったので映画も見ました。サブスクでは、アニメタイムズ(30日間無料体験)で視聴できるようです。
映画を見てから小説を読んだので展開はわかっていましたが、本で読んだ方が自己の内面についてじっくり考えさせられました。周囲や社会が求めているものに応え続ける善良さ、不正解を避けてきただけの人生なのに自分に募る自己愛、選択をする場面になったときに現れる無自覚な傲慢さ、そんな人間心理を描いた物語でした。
婚活で値踏みをする傲慢さ
『傲慢と善良』の物語は、現代の婚活がテーマです。その中で描かれている「傲慢さ」は、マッチングアプリや婚活をしたことある人なら誰でも思い当たる節があるものだと思います。何人もの異性と会ってその中から自分に会った人を探す、言い方を変えれば、相手が自分に相応しいかどうかを判断する。これを作中では、相手の評価を数値化したり、「値踏みする」という表現がよく使われていました。更にそれは「自己評価の裏返し」でもある、と。
婚活で「なんでこんなにいい人がいないのだろう?」という気持ちにはなったことある人は多いはずです。私もマチアプをしている友達と「アプリはろくな人いないよね」なんて話をしたこともあります。でもこの作品を読むとこれこそが傲慢さなんだと気付かされたます。
そこ(これまで自分が歩んできた道)に自分の意思や希望はないのに、好みやプライドとーー小さな世界の自己愛があるから、自由になれない。いつまでも苦しい。(文庫p282)
自分なんて大したことないと自己評価は低いくせに、恋愛となると、ご立派な好みやプライドによって真摯に相手と向き合うことができない。相手と数回話しただけで悪いところばかり見つけて、自分には見合わないと評価する。
自分の意思を持って自分の道を選ぶのではなく、与えられた選択肢から不正解を避け続ける減点法で生きてきてしまった人は、ポジティブな方面に道を選ぶことよりも間違いを選びたくないという気持ちが先に働き、だからこそ相手の悪いところばかりに目がいってしまう。そしてどうして自分だけはいい人を見つけられないのかという気持ちで苦しむ、と言うことがさまざまな描写で表現されていました。
作中で「あなたがいい」と「この人ならいい」という言葉が出てきたページがありました。
これまでずっと「いい人がいない」と言い続けていて、あなたと出会って、「この人ならいい」と思った。つきあうことになって、これでもう二度と惨めな思いをしないで済むと思ったのに。もう大丈夫だと思ったのに。(文庫p336)
「この人ならいい」という言葉は、自己愛の高さと傲慢さをよく表している言葉だと感じました。自分に見合った相手をようやく見つけたといった心理がよく現れている言葉だなと。
自己評価と関連用語
作中に出てきたのは「自己評価」「自己愛」という言葉でしたが、似た言葉で「自己肯定感」「自尊心」はよく使われる言葉です。これらの言葉の関係性や違いが気になったので関連する言葉の意味を調べてみました。
自己肯定感と自尊心
自己評価は自分の能力や性格、行動について自分で下す判断、つまりは自分に対する採点ですが、自己肯定感は、ありのままの自分を「これでいい」と肯定できる感覚です。自己評価が高い・低いに関わらず、無条件に自分の存在を受け入れる心の状態を指します。
自尊心は自分に抱く誇りや尊厳の意識です。「自分は尊重されるべき存在だ」と思う気持ちで、プライドに近い意味を持ちます。自尊心は傷つく、保つという動詞と使うように、他人との関係の中で維持するもので、鋭く反応する防衛本能的な感情でもあります。
自己肯定感は自分を支える土台で、自尊心は壁や鎧のようなイメージが近いと思っています。自己肯定感が低いと自尊心は過剰(過敏?)になってしまうこともあり、大きく傷ついたり、自己防衛のために過剰に相手を攻撃したり虚勢を張ったりしてしまいます。
自己愛
自己愛は自分自身を愛し、大切に思う感情のことです。広い意味では「自分を尊重する健全な気持ち」ですが、文脈によっては「自分ばかり可愛がる、わがままな態度」というネガティブな意味で使われます。
健全な自己愛は、自己肯定感や自尊心と結びついて、ありのままの自分を認める態度ですが、過剰な自己愛は、ナルシズム(自己陶酔)につながり、自分に酔いすぎたり他人を見下したりする態度を指します。
自己効力感
自分との関係で生まれる感覚には自己効力感もあります。自己効力感は「自分には何かを成し遂げる力がある」と信じる感覚で、経験や成功体験から育つものです。自己効力感は自己肯定感を支えるものでもあり、これが高いと挑戦をできる人になります。
承認欲求と自己有用感
他者とのつながりや社会の中での自分の存在価値に深く関係する感覚には、承認欲求と自己有用感のふたつの感覚があります。似た感覚ですが、その求め方や手応えの質が異なります。
承認欲求は他人から評価されたい、認められたいという欲望です。強すぎると「他人の目」に依存しやすくなるほか、欲求なので、満たされなければ不満や不安が生まれます。一方、自己有用感は自分は誰かや社会の役に立っていると感じられる感覚(貢献の気持ち)です。他者との関係性の中で育まれ、特に感謝されることや必要とされることで高まります。
承認欲求は、「承認されたい」という外向きの動機で、自己有用感は「誰かの役に立てる」という内向きの充足です。承認欲求は誰しも持つものですが、それが自己有用感へと育つことで、「他人の評価」でなく「他人への影響」で自分の価値を感じるようになります。承認欲求は一時的な嬉しさや安心感を得ることができますが、自己有用感では持続的な充実感を得たり、存在価値を感じることができるものです。
心理概念マッピング表
今まで紹介した「自尊心・承認欲求・自己効力感・自己有用感・自己肯定感・自己愛」を、動機の発生源(内発的・外発的)と動機の向かう先(利己・利他)で分類できると思い、表にしてみました。
| 利己(自分のため) | 利他(他人のため) | |
|---|---|---|
| 内発的動機 (意思的・持続的) | 【自己マスタリー領域】 自己効力感:自分にはできるという信念 自己肯定感:ありのままの自分を認める 自己愛(健全):自分を大切にする感覚 | 【貢献・使命感領域】 自己有用感:人の役に立てているという実感(自分の内から満足) |
| 外発的動機 (単発的・反応的) | 【承認・競争領域】 自尊心:他人からの評価を通じて「自分は価値がある」と思える感覚 自己愛(過剰・ナルシシズム的):他人より優れていたい、特別でいたい | 【所属・関係性領域】 承認欲求:他人に認められたい、褒められたい、評価されたいという欲求 |
内発的な感覚(自己との関係で生まれる感覚)は、持続的で安定しやすいものです。外発的な欲求(他者との関係で生まれる欲求)は、入り口として有効ですが、長期的な充足にはつながりません。長期的に安定させるには、内発的な動機への転換が必要になります。また、利己から利他へのシフトは、精神的成熟を促すプロセスでもあると言えます。
マツコ・デラックスがマツコ会議で「幸福とは他者を介在させないこと」と言っていましたが、まさに動機の発生源を外発的なものから内発的なものへと転換させていくことの重要性を語っていたんだと感じます。人と関わらないで幸せを得るということではなく、自分のことは自分で愛し、他人との関わりの中でも見返りを求めずに純粋なる貢献の気持ちで行動する、そうすることで人に依存することなく役に立ったという事実だけで幸せを感じることができる、ということを言っていたんだろうなと。
「傲慢さ」は基本的に利己的な感情であり、他人を利用する視点から生まれるものです。利他的に見える行動でも、実は自分の承認欲求や支配欲のためだったりもします。真の利他性は、そこに我欲がなく、優越感も見返りも求めない状態です。本当に「無私の欲」で行動するのはとてもハードルの高いことですが、意識することは重要だと思いました。
まとめ
『傲慢と善良』では、主人公である西澤架は、ルックスが良く、周りの目を気にせず行動する傾向があり、交際を始めても将来を決めないなど、傲慢さを持った人物として描かれていました。恋愛経験も豊富で、自己肯定感も高く、他者に依存せずとも精神的に安定しているからこその傲慢さを持っていました。恋人である坂庭真美の失踪により、そうした自分の傲慢さと向き合っていきます。
一方で、真実は恋人や結婚を承認欲求を満たすために利用していました。献身的(利他的)に見えて本質的には利己的な部分もあり、自己愛が強い人物として描かれています。基本的には控えめで謙虚で自分の意思は薄いものの、恋愛における好みやプライドは持っており、他者を利用して幸せになろうという利己的な考えも根本的には存在し、それが傲慢さとして描かれていました。
自己評価の高さからくる傲慢さを、内発的な自己肯定感からくるものと外発的な自己愛からくるもの、それぞれが対比で描かれており、日常にある人間心理をここまで解像度高く理解しそれを描写していて、とてもすごいと思いました。
婚活に悩みを持つ方は、どちらの登場人物に対しても共感するところがあると思います。恋愛における人間心理に興味がある方はぜひ読んでみてください。
おわり。